自筆証書遺言とは、遺言者自身で書く遺言書です。
したがって、書き残すという面のみからみると、紙とペンさえあれば、簡単に作成できるだろうとも感じられます。
しかし、遺言者が亡くなった後で、その自筆証書遺言が本当に遺言者の意思を示したものであり、偽造されたものではないことを証明できる遺言書とするためには、その遺言書が様々な条件を満たしている必要があります。
それらの条件をしっかりと満たした自筆証書遺言を作成することで、相続発生時に法的に無効な遺言書として扱われてしまうことを防ぐことができます。
このページでは、自筆証書遺言を書くにあたって、注意すべき点について説明いたします。
自筆証書遺言を作成するにあたり注意すべき点
自筆証書遺言を作成するにあたって、紙の種類やペンの種類(ボールペンや万年筆)等の規定はありません。
書式についても特段の規定はなく、縦書きでも横書きでも構いません。
ただし、消えてしまうリスクを考えると、鉛筆や消すことができるボールペンでの作成は避けるべきでしょう。
また、紙についても保存に適した用紙を選んでください。
以下については特に留意して作成する必要があります。
自書について
遺言の内容、日付、氏名を、全てご自身で書き、捺印してください。
ご自身で書き記すことによって、本人が作成したことの証明になります。
したがって、パソコンでの作成は不可となります。
ただし、相続財産の目録を添付資料としてつけるとき、その添付資料は自書不要とされています。
したがって、目録をパソコンで作成したり、書類そのものを添付する(例えば通帳のコピーを添付する等)ことはできます。
(ただし、添付する目録の1ページごとに署名、捺印が必要です)

日付について
遺言書の中に、作成した日付を必ず書き記してください。
遺言書が複数発見されたとき、原則、後に作成された遺言書が優先されることになっています。
また、遺言能力の有無(作成時、認知症にかかっていなかった等)を判断する材料としても、作成日は非常に重要になります。
したがって、作成年月日がしっかりと記載されていることは大切です。
「〇○○〇年×月吉日」などのあいまいな表記をせず、作成日をしっかりと書き残してください。
書き損じ箇所について
全文を自書しなければならない自筆証書遺言では、作成中に書き間違えることが多々あります。
書き間違えてしまった場合、修正テープで修正するなど、ご自身の思う方法での修正をしないでください。
自筆証書遺言では、書き間違えた場合の対処方法が、民法でしっかりと規定されています。
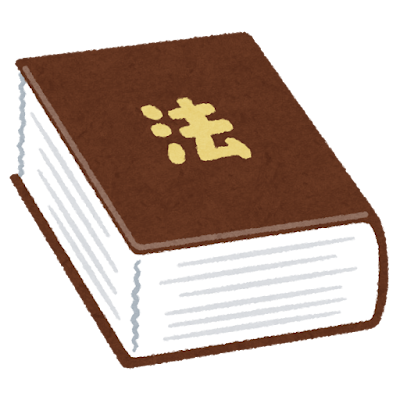
自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

自筆証書遺言では作成者以外の者によって書き換えられていないということをはっきりさせる必要があり、この対処法を遵守していることが大切です。
書き間違えてしまった場合は、(大変な作業にはなりますが…)遺言書全体を書き直すことも検討してください。
自筆証書遺言においては、せっかく作成した遺言書が後に無効とならないために、形式を守って作成することが大切です。
個々のケースにより守るべきポイントがそれぞれ生じますが、本ページでは「自書」「日付」「書き損じ」の3点に焦点をあてて説明いたしました。
遺言書の作成を検討する際は、自筆証書遺言においてはこのように形式を守ることが大切であること念頭に、ご自身にあった種類の遺言書を選んでください。
さんご行政書士事務所では、
遺言書を遺すことを検討している相談者様からお話をお伺いし、遺言書作成のサポートをいたします。
