古物営業を開始する場合、公安委員会から古物商許可を得る必要があります。
申請書類の提出先は、営業所(古物営業を行う拠点)の所在地を管轄する警察署です。(警察署を経由して公安委員会に提出されます)
許可を得ずに営業した場合、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金が科される可能性があります。

また、許可を得て古物営業を開始した後も、営業内容に変更が生じた際には変更届け出書を提出しなければなりません。
本ページでは、古物商許可申請を提出する前の書類準備段階において検討すべき主な5つの点についてご説明いたします。
申請書類等の準備段階で検討すべき事項
書類の作成から提出までをより円滑に進めるために、古物商許可申請の書類準備段階において確認すべき主な5つの点を以下に挙げます。
- 個人で申請するか、法人で申請するかの確認
- 営業所の場所の確認
- 取り扱う古物の品目の確認
- 欠格事由に該当する人がいないことの確認
- 管理者が適正かどうかの確認
以下でそれぞれの項目について説明していきます。
1.個人で申請するか、法人で申請するかの確認
古物商許可申請には、個人用の申請書と法人用の申請書があります。
法人名義で営業を行う場合は法人として許可を得る必要があります。
法人の役員の一人が個人名義の古物商許可を取っていたとしても、法人名義での古物営業はできません。
まずは、個人として許可を受けるのか、法人として許可を受けるのかを決定してください。
これにより、申請書のみならず準備すべき添付書類も異なってきます。
2.営業所の場所の確認
営業所とは、古物の売買、交換、レンタル等を行う拠点となる場所です。
原則、申請時に営業所の住所等を記載する必要があります。
古物商許可申請は、この営業所の所在地を管轄する警察署を経由して、都道府県の公安委員会に提出されます。
したがって、どの場所を営業所にするのか、そしてその営業所が古物営業を行う場所として適正かどうかを確認してください。
営業所を選ぶ際の注意すべき点として、営業所は、申請者がその営業所の使用権原を持っている必要があるということが挙げられます。
賃貸物件や集合住宅を営業所として登録する際は、要注意です。
契約書や規約の使用目的の欄に「居住専用」や「営業活動を禁止する」等の文言がある場合や、申請者と賃貸借契約等の契約者が異なる場合は「承諾書」等が必要となる可能性があります。
また、申請した営業所の実在性や独立性も審査の対象となります。
実在性とは、その住所に営業所が実際に存在する(バーチャルオフィス等ではないか)かということです。
独立性とは、その営業所の独立性が保たれている(古物台帳等が適正に管理されるか等)かということです。
ただし、営業所の要件(審査時に求められる条件)や提出を求められる添付書類等については、都道府県や管轄の警察署によって若干異なる場合があります。
検討している場所が営業所として認められるのか、承諾書等の追加資料が必要になるのか等について迷ったときは、提出先となる警察署等に相談することをお勧めいたします。
3.取り扱う古物の品目の確認
古物営業を行うにあたって取り扱う「古物の品目」を確認してください。
古物営業法施行規則により、「古物の品目」は次の13品目に分類されています。
| 1.美術品類 | 6.自転車類 | 11.皮革・ゴム製品類 |
| 2.衣類 | 7.写真機類 | 12.書籍 |
| 3.時計・宝飾品類 | 8.事務機器類 | 13.金券類 |
| 4.自動車 | 9.機械工具類 | |
| 5.自動二輪車及び原動機付自転車 | 10.道具類 |
古物商許可申請書では、これら13品目の中から取り扱う予定のある品目を選んで、申請書に記載します。
選び方としては、まず、一番メインで扱う品目を1つ選んでください。
これが「主として取り扱おうとする古物」になります。
さらに、メイン以外で扱う予定の品目も選んでください。
これが「取り扱おうとする古物」になります。
「主として取り扱おうとする古物」は1品目だけしか選べませんが、「取り扱おうとする古物」は複数選ぶことができます。
ただし、許可取得後に、選んだ品目のなかで盗難事件があった場合、警察署に情報提供などの捜査協力が必要となります。
4.欠格事由に該当する人がいないことの確認(申請者、法人役員)
古物商許可申請では、申請者や法人役員(法人申請の場合)が欠格事由に該当してしまうと申請許可が下りません。
したがって、申請前に、各々が欠格事由に該当していないかを確認する必要があります。
では、『欠格事由に該当する』とはどのような場合でしょうか。
古物商許可申請の欠格事由については、古物営業法に記載されています。
古物営業法第4条において、古物営業の許可を受ける者が次の1~11のいずれかに該当する場合、古物営業の許可をしてはならないと規定されています。
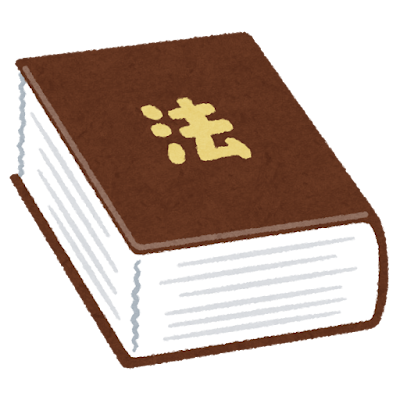
第4条
公安委員会は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は第三十一条に規定する罪若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百三十五条、第二百四十七条、第二百五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
- 住居の定まらない者
- 第二十四条第一項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)
- 第二十四条第一項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第八条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して五年を経過しないもの
- 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第十一号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
- 営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は古物市場ごとに第十三条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
- 法人で、その役員のうちに第一号から第八号までのいずれかに該当する者があるもの
申請者、法人役員(法人申請の場合)の中に、これらの項目に該当する可能性のある方がいらっしゃるかどうかを、申請書準備段階で確認する必要があります。
5.管理者が適正かどうかの確認
古物営業法第13条において、管理者一人を営業所ごとに選任しなければならないと規定されています。
したがって、古物商許可申請時には、営業所の管理者を明記する必要があります。
1つの営業所ごとに一人の管理者を選び、その管理者が管理者として適正かどうかを確認してください。
管理者とは、業務を適正に実施するための責任者であり、営業所の古物取引に関して管理・監督・指導ができる人のことです。
したがって、誰でも管理者になれるわけではなく、許可申請の際には、この管理者が、管理者として適正かどうかが審査されます。
管理者として適正かどうかの主な基準として、ここでは2点を挙げます。
管理者としての適性基準
1.欠格事由に該当しないかどうか。
管理者の欠格事由が古物営業法第13条において規定されております。
その内容は、上記の「4.欠格事由に該当する人がいないことの確認」と類似しています。
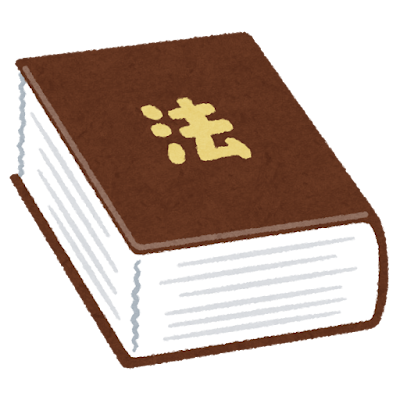
第13条第2項
次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない。
1.未成年者
2.第四条第一号から第七号※までのいずれかに該当する者
3.心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
※第四条第一号から第七号とは、上記「4.欠格事由に該当する人がいないことの確認」に出てきている古物営業法第4条内の1~7にあたります。
したがって、申請者や法人役員のみならず、管理者も欠格事由に該当してないかの確認が必要となります。
2.管理者として必要な知識、技術、経験を有しているか。
管理者として適正かどうかの審査には、管理者として必要な知識、技術、経験を有しているかどうかの審査も含まれます。
特に、「3.取り扱う古物の品目」において、自動車、自動二輪車又は原動機付自転車や、時計、宝飾品類を入れている場合、申請時に警察署の担当者から、知識や技術を持ち合わせているかどうかの確認がされる可能性があります。
古物商許可申請においてはこれら等の基準をもとに、管理者が適正であるかどうかが審査されます。
ただし、管理者の適性基準については、都道府県や提出先となる警察署によって若干異なる可能性があります。
管理者として認められるかどうか迷ったときは、提出先となる警察署等に事前に相談することをお勧めします。
本ページでは、古物商許可申請の書類準備段階において確認すべき主な5つの点についての説明いたしました。
(あくまでも主な5点に焦点をあてています。そのため、実際の申請準備においては、個別の案件ごとに検討すべき点がこれら以外にも出てきます。)
確認事項の中でも言及しておりますが、古物商許可申請においては、必要な添付書類や要件等が都道府県や管轄の警察署によって若干異なる場合があります。
したがって、申請予定の内容に即した書類の準備を行った上で、提出予定の警察署において申請書提出前の事前相談をすることをお勧めいたします。
さんご行政書士事務所では、
古物商営業許可申請書の提出を検討している相談者様に対し、申請書作成から提出までの総合的なサポートを行います。
なお、申請内容に対する最終的な許可判断は、あくまでも公安委員会により下されます。
提出段階で基準を満たしているとして申請、受理されたとしても、公安委員会により許可/不許可の判断が下されることをご了承ください。
