自分が持っている土地が農地なのか?
何を基準に農地とされるのか?
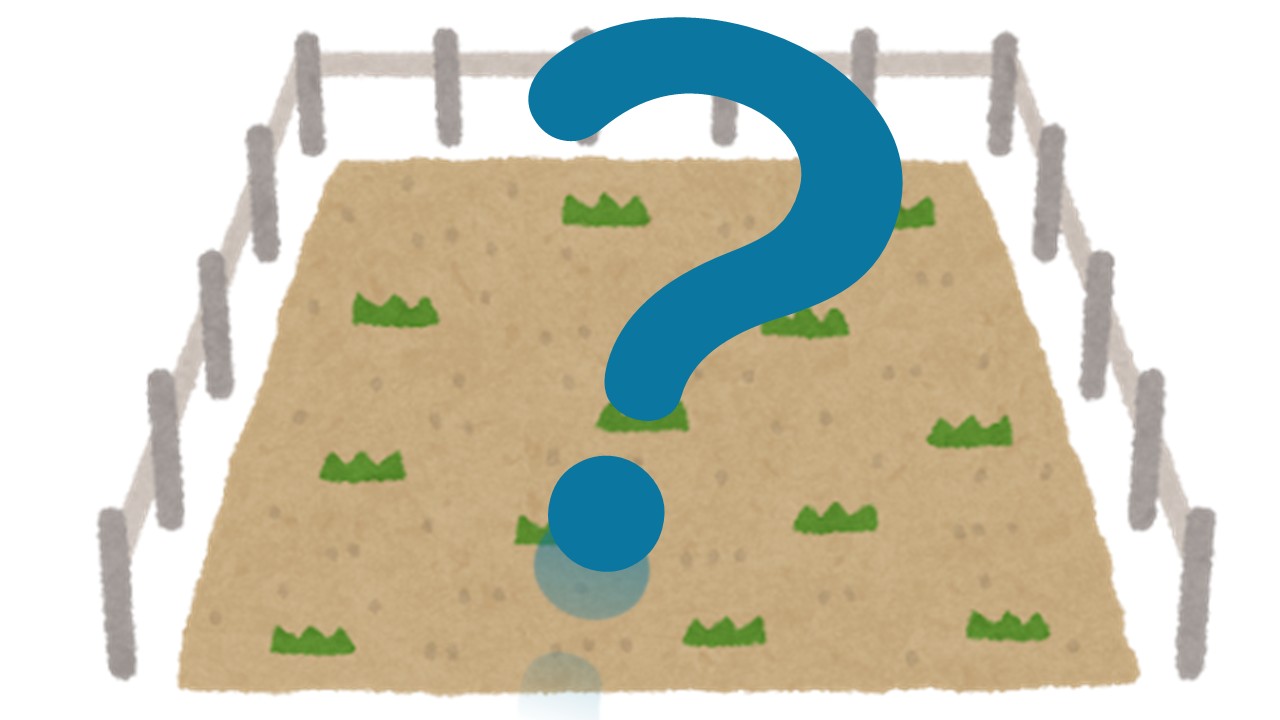
私自身、農地関連の手続きに関わり始めて、最初に浮かんだ疑問は、この『なにをもってして農地というの?』でした。
結論から述べると、
農地法関連の手続きにおいては、
その土地が農地として使われている土地であるかどうか
によって判断されます。
この判断の仕方、当たり前のことを言っているようですが、農地関連の手続きにおいてはとても大切な考え方となっています。
「その土地が農地として使われている土地かどうか」、つまり「現在の状況によって農地かどうかを判断する」考え方のことを『現況主義』と言います。
ここでは、この農地法における『現況主義』というものがどのようなものなのかを説明いたします。
農地法における現況主義
上述のように、農地法においての農地かどうかの判断は、その土地が「農地として使われている土地」であるかどうか、つまり、その土地の状態に基づいて客観的に判断されます。
(「農地として使われている土地」には、耕作が放棄されている土地や耕作をお休みしている土地(耕作放棄地や休耕地)も含まれます。)
つまり、農地法においては、その土地の登記簿上での地目は関係なく、農地がどうかが判断されるということになります。
(土地の登記簿には、『地目』という欄があり、宅地や山林、田、畑、原野など、その土地の主たる用途が記載されています)
例えば、土地登記簿上で地目が「宅地」となっていたとしても、その土地の現在の状態(現況)が農地であれば、農地法的には「農地」と判断される、ということになります。
登記簿上の地目が宅地になっていたので、農地法上の手続きは必要ないと判断してしまうのは危険です。
現況主義に基づいて、農地であると判断された場合、違法転用していたという事態に陥ってしまいます。
このように、ある土地が農地かどうかは、登記簿等の書類に記されているわけではありません。
農地かどうかの判断は、自己判断せず、売買や賃借、転用する前に農業委員会等に相談するようにしましょう。
