所有している農地を農業以外の用途(宅地、資材置き場、駐車場等)で使用する場合(農地転用)、農地法第4条に則り、原則、農業委員会等に申請書類等を提出する必要があります。
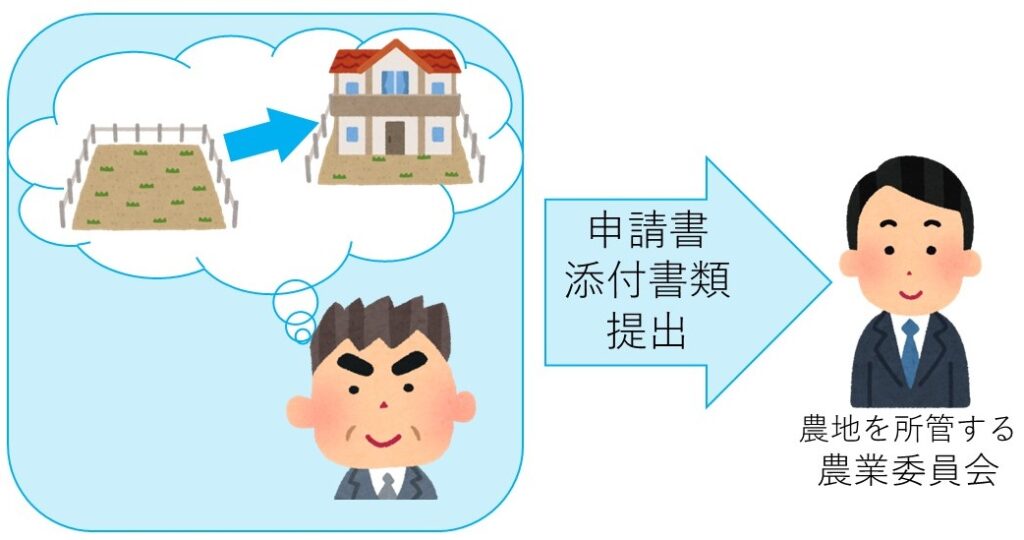
農地転用においては、許可申請書を提出すると自動的に許可がおりる、というわけではありません。
許可権者(許可/不許可を判断する機関)である行政機関等は、申請内容が転用を許可するための要件を満たしているかどうかを審査したうえで許可/不許可の判断を下します。
では、許可の判断をする行政機関等はどのような基準をもとに、許可/不許可を判断しているのでしょうか?
農地転用においては、許可するための基準として、立地基準と一般基準という2種類の許可基準が設定されています。
そして、申請時にこの2種類の基準を満たしていると判断されない限り、農地転用の許可は下りません。
このページでは、この農地転用における一般基準について説明します。
農地転用における一般基準とは
一般基準とは、立地基準以外の基準を総称するもので、様々な基準が法令において定められています。
様々な基準が定められている一般基準ですが、基準の内容により、大まかに2つの種類に分けることができます。
- 転用後その土地が確実に活用されるかどうかを判断するための基準(申請目的実現の確実性についての基準)
- 周辺農地の農業に支障を与えないかどうかを判断するための基準(周辺農地の営農条件への支障についての基準)
以下でそれぞれの基準について説明していきます。
1.転用後その土地が確実に活用されるかを判断するための基準
(申請目的実現の確実性についての基準)
農地転用では、「とりあえず、転用の許可だけとっておこう」という申請は認められません。
農地を守る立場にある農地法における農地転用では、転用後その土地をどのように利用するのか(転用目的)そして、その目的をどのように達成するのか(転用後の事業計画)の提出が求められます。
転用目的においては、例えば、住宅を建てる、駐車場を作る、資材置き場を設置する、太陽光発電事業を行う等の目的を明示する必要があります。
転用後の事業計画においては、設置予定の施設の概要や事業の操業期間、設置施設の利用期間のみならず、事業遂行にあたって必要となる資金の調達計画等の提出が求められます。(例えば、自己資金を予定しているのであれば預金の残高証明、融資を検討しているのであれば融資証明書等が必要となります)
また、農地転用の妨げとなる権利を有する者がいる場合、その方たちからの同意を得ているかどうかも問われます。例えば、その土地に賃借権がついていたり、土地自体に共有者がいる場合です。
このように、農地転用の一般基準においては、転用後にその土地が申請時の目的通りに活用されるかどうかが審査の対象となり、転用後に申請目的に沿った活用がなされないと判断された場合、転用申請に対して許可が下りません。
2.周辺農地の農業に支障を生じさせないこと
(周辺農地の営農条件への支障についての基準)
周辺の農地における農業活動に悪影響を及ぼす可能性のある転用に対しては、許可がおりません。
例えば、
舗装した駐車場にした結果、雨水が隣の畑に流れ込むんでしまった。
盛り土を行った結果、その土が隣の農地に流れ込んでしまった。
新しく建築した建物が太陽光を遮ってしまい、隣の畑でこれまで通りの農業ができなくなってしまった。
などの事態が起こることさけるためです。

農地転用の許可申請提出時には、これらの事態をさけるため、転用農地付近の土地や作物等に被害を与えないための対応策を記入します。
そして、周辺農地の農業に悪影響を及ぼす可能性がある場合、それに対する措置を講じることを明記する必要があります。
(周辺農地の農業に支障があると評価されてしまうと、許可が下りません)
本ページでは、農地転用における一般基準について焦点をあてました。
一般基準においては、農地法(第4条第6項第3号から第6号)において規定がおかれており、上記のような基準をもとに審査が行われます。
しかし、これらの基準に対してどのような書類の提出が求められるのかの詳細については、自治体ごとに異なってくる場合もあります。
したがって、農地転用を検討する際は、上記基準を理解した上で転用目的に対する計画をしっかりと立て、担当の行政機関等と調整していく必要があります。
さんご行政書士事務所では、農地の転用を検討している相談者様に対し、
現地調査(農地の現状把握)から、行政機関等との相談、申請書の提出までの総合的なサポートを行います。
なお、申請内容に対する最終的な許可判断は、あくまでも行政機関等の許可権者により下されます。
提出段階で基準を満たしているとして申請、受理されたとしても、行政機関等により許可/不許可の判断が下されることをご了承ください。
