遺言書とは、遺言書を残す人が、自身が亡くなった後に財産をどのように分けてほしいかという意思を記しておくものです。
遺言は作成者の最終意思を尊重する制度であるため、遺言者は財産を誰にどのように配分するかを自由に記し遺すことができます。(後述しますが形式には決まりがあります)
そして、この遺言書は、原則、遺言者が亡くなった時点から効力を生じ、遺言書の通りに遺産を分けることができるようになります。


一方、遺言書がない場合、相続人同士の話し合いによって財産(遺産)の配分方法や割合を決めます。
この話し合いのことを、「遺産分割協議」と呼びます。
(遺産分割協議が不要の場合もあります。例えば、相続人が一人しかいない時などです。)
遺産分割協議では、原則、相続人全員が参加しなければならず、また相続人全員が協議内容に合意する必要があります。(相続人とは亡くなった方の遺産を相続する人ですが、誰が相続人に該当するのかは民法で定められています。)
遺産分割協議で合意することができなかった場合は、裁判所における調停や審判で相続分を決定することになります。
(注:必ずしも、テーブルを囲んだ会議のようなものを開催しなければならないわけではありません。大切なのは、相続人全員の合意をとることです。)
遺産分割協議では、相続人間の話し合いがうまくまとまり、相続人全員が納得する内容の相続手続きへとつながることが理想的といえるのかもしれません。
しかし実際には、遺産分割協議による話し合いがうまくいかず、家族や親族間の関係がこじれてしまうことがあります。
また、分割協議の合意には至ったものの、実は内容に納得がいかない相続人がいて、家族や親族間の関係が疎遠になってしまったり、関係がこじれてしまうこともあります。
また、そもそも相続人間の関係が疎遠で、話し合いの場を設けることが難しい(遺産分割協議をすること自体に苦労が伴う)こともあります。
つまり遺言書を遺しておくことで、遺産分割協議を経ることなく相続の手続きを開始できるようになるため、残された家族の相続における手続きの負担を減らす(遺産分割協議が不必要になる)ことができるだけでなく、残された家族の間でトラブルが起こる可能性を軽減することができるのです。
このように遺言書には
- 遺言を遺す者にとってのメリット
- 自身の財産の配分方法についての意思を、事前に記しておくことができる。(遺留分の侵害に注意)
- 遺された家族にとってのメリット
- 家族・親戚間で起こりうる争いごとを軽減する。
- 相続における手続きをより簡易にする。
という、遺す者と遺された家族という2者にとってのメリットがあります。
しかし、一口に「遺言書」といっても、どのような形式の遺言書でも法的に認められるわけではありません。
(法的に認められる遺言書でないと上記のメリットを発揮することができません)
遺された遺言書が、遺言者の意思を本当に反映したものであること、偽造されたものではないこと等を立証できるようにしておくために、法的に遺言書の書き方が決められているのです。
法的に認められる遺言書の形式としては主に以下の3種類があります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
以下で、それぞれの遺言書の特徴についてご説明いたします。
1.自筆証書遺言
遺言者自身が自筆で書く遺言書です。
公証人の関与なしに作成できるため、手続きの数が少なくご自身で気軽に作成できます。
しかし、形式が定められており、その形式が守られていない場合、相続が発生した時(遺言者が亡くなった時)に、遺言書自体が無効(遺言書の通りに相続が行えない)になってしまう可能性があります。
したがって、遺言書作成時点で形式を守って作成することが非常に大切です。

2.公正証書遺言
遺言者の意思の通りに公証人により作成され、公証役場で保管される遺言書です。
作成時には公証役場で証人2名の立ち合いが必要とされます。
公証人が関与するため自筆証書遺言に比べ、手続きの数が多くなり、また作成費用も高くなる傾向があります。
その一方で、公証人が中身を確認しているため、自筆証書遺言に比べ遺言書が無効になる可能性は低くなります。

3.秘密証書遺言
遺言の内容を誰にも知られずに作成する遺言書です。
自身で作成した遺言書を封印した後に、公証役場にて公証人および証人2名の前で、その遺言書が間違いなく遺言者本人のものであることを明確にします。
公証人の関与があるものの、その関与が限定的で、公証人も証人も遺言書の中身を確認することはありません。
したがって、中身の形式に不備がある等が発見されにくく、遺言書が無効になる可能性があります。
手続きの数が多いうえに無効になる可能性があるため、実際にはほとんど使われていないといわれています。
前述の通り、相続の発生時に法的に認められる遺言書にするため、法に則った形式で遺言書を作成することが大切です。
そのために、一般的にはこれら3種類(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)の形式の中から、ご自身に一番合う形式の遺言書を選んで作成する必要があります。
「秘密証書遺言」が存在しているがゆえに、「公正証書遺言」や「自筆証書遺言」では遺言書の内容を相続人に知られてしまうのではないかと心配をされる方がいらっしゃいます。
しかし、例えば公正証書遺言であっても、遺言書を遺す方が遺言の内容を相続人に知られたくないと希望する場合、守秘義務を持つ第三者(弁護士、司法書士、行政書士※等)を証人にすることで、相続人に内容を知られずに作成することができます。
まずは、遺言書作成の必要性も含め、遺言者がどのような形で遺言書を遺したいと思っているかを整理したうえで、適切な方法での遺言書の作成を検討することが大切です。
遺言書の作成を検討する過程では、自身がどのような財産をどれくら持っているのか確認したり、自身がこれまでどのような方々とどのような形で関わってきたのかを考える機会をもつことになります。
遺言書の作成を検討した結果、遺言書は作成しないという結論に至ったとしても、その過程が貴重な時間だったと考える方も多くいらっしゃいます。
まずは、『遺言書を遺す』という選択肢があることを念頭に、自身の財産を整理したり、これまでの自身の歩みを振り返ってみるのもよいのかもしれません。
さんご行政書士事務所では、
遺言書を遺すことを検討している相談者様からお話をお伺いし、遺言書作成のサポートをいたします。
※行政書士には、法律で定められた守秘義務が課されています。
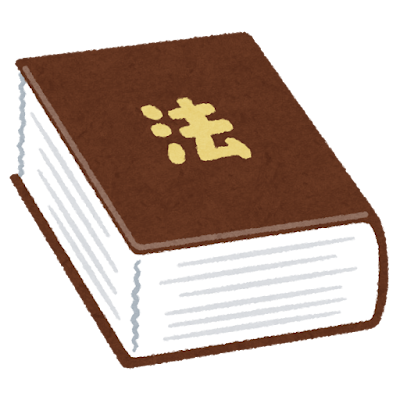
第12条
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
第19条の3
行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者でなくなった後も、また同様とする。
第22条
第12条又は第19条の3の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
このように、行政書士には相談者様の相談内容を外部に漏洩させない責務があります。
安心してご相談ください。
